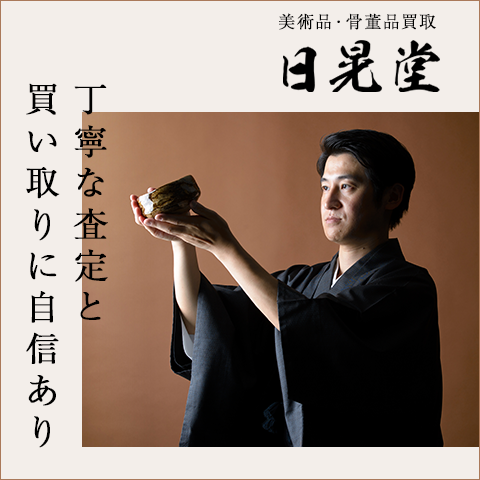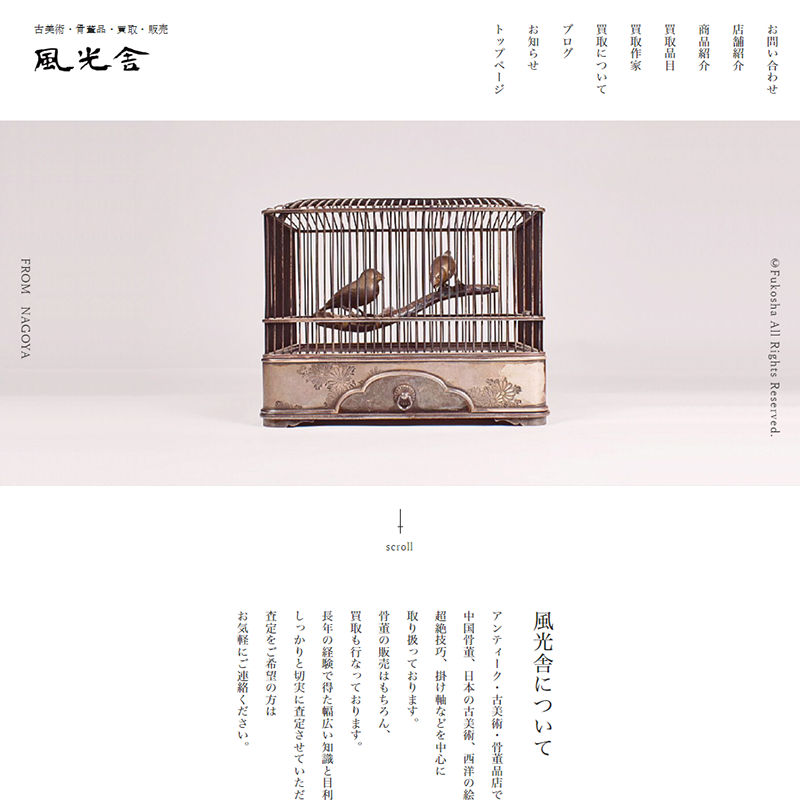薩摩切子の歴史と骨董的価値
薩摩切子は「幻の切子」とも呼ばれている
薩摩切子とは、幕末から明治時代の初めにかけて薩摩(鹿児島)で作られていたカットグラス(切子)の総称です。
薩摩切子は、薩摩ビードロや薩摩ガラスとも呼ばれ、1851年(嘉永4年)に薩摩藩の第11代藩主となった島津斉彬の指示によって、外国との交易品や大名たちへの贈答品として開発され、急激に発展していきました。しかし、島津斉彬が49歳で急逝するとともにその製造は一気に衰退していきました、
薩摩切子の歴史は1877年に一度幕を閉じてしまったため、薩摩切子は幻の切子と呼ばれるようになりました。現在では復刻版が製造・販売されていますが、昔の薩摩切子は「古薩摩切子」と呼ばれ、現在のものと区別されています。
他の切子の中では江戸切子も有名ですが、江戸で作られた江戸切子が庶民の日用品として使用されていたのに対して、薩摩切子は島津藩の御用達として製造されたため贈答品や観賞用として使用されてきました。
このような歴史を持つ薩摩切子は骨董市場でも高値で取引されることがあり、特に古薩摩切子には高い価値があります。